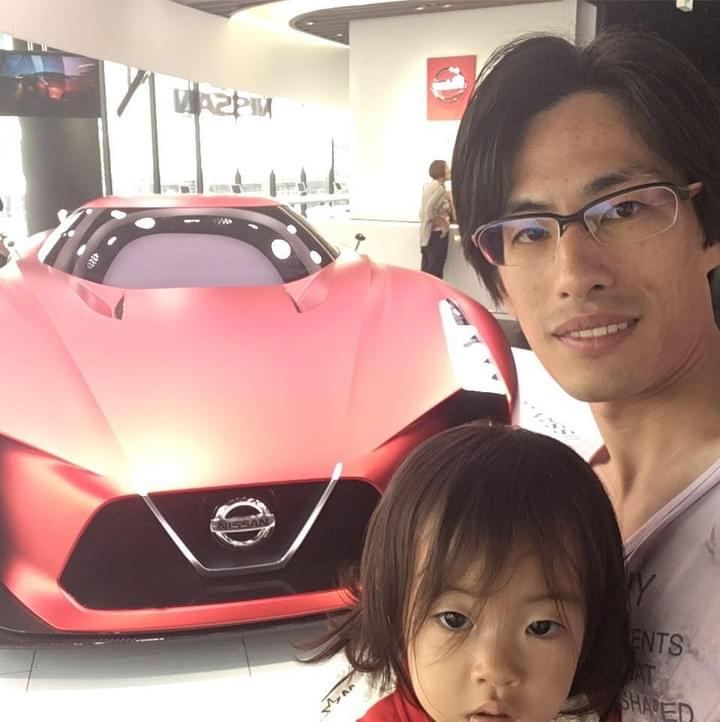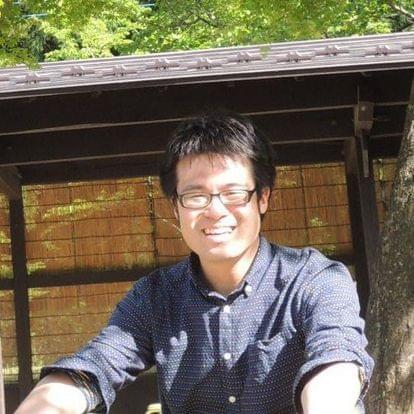DAISUKE
ISHII

COVID-19に対抗する
AI技術&事例研究本
2021/1/19翔泳社より発売。医師AI起業家・ITコンサル・AI研究者の共著。台湾のデジタル大臣オードリー・タン氏の特別インタビュー付き。
AIは絶望のなかで希望の光になれるのか?
概要
コロナ vs. AI 最新テクノロジーで感染症に挑む(翔泳社)
AIで新型コロナウイルスを封じ込める!
画像認識、自動運転などAIの利活用がさまざまな分野で進んでおり、
IoTなどの技術と合わせて産業構造が大きく変化しています。
医療分野においても技術の進展は急速であり、
さまざまな病気の治療にも最先端の技術が活用されています。
これらの技術はコロナ対策においても、さまざまな分野で利用されています。
【本書の概要】
・AIを中心にコロナ対策に活用されている最新テクノロジーを紹介
・活用例は治療だけにとどまらず、「予防」「スクリーニング」「創薬」「公衆衛生」「除菌」など幅広く紹介
・AIだけでなく、コロナ対策に活用されているロボットの事例も紹介
・まだ実用化はされていないが、今後の活用が期待される事柄も紹介
・AIの論文をいくつか取り上げ、どのようなシーズが作られているのかを紹介
【豪華二大特集】
台湾のIT担当大臣オードリー・タン氏のインタビューも掲載。
同氏の見るコロナウイルスvs.デジタルという視点は、
今後の新型コロナウイルスとデジタルとの付き合い方を考えるうえで大いに参考になります。
また、著者の一人石井大輔氏は新型コロナウイルス患者として医療現場で働く医師や看護師と接することになりました。
現場のリアルな苦闘もエンジニアの視点からレポートします。
目次
【目次】
第1章 vs.コロナのために押さえておくべきAIの動向
第2章 新型コロナウイルスとAI(取組事例)
第3章 新型コロナウイルス関連のAI論文
第4章 vs.コロナのために押さえておくべきロボットの動向
第5章 新型コロナウイルスとロボット(取組事例)
第6章 Withコロナ、Afterコロナの展望
特別付録
Interview オードリー・タン台湾デジタル担当大臣との対話
感染してわかった新型コロナウイルスの恐ろしさと今後への気付き- YouTube共著者トーク & 台湾オードリー・タン デジタル担当大臣 特別インタビュー
はじめに
AIとロボットでコロナウィルスに立ち向かう新型コロナウイルスは否応なく私たちの生活を急激に変化させました。古い慣習が続いていた大企業でもテレワークが当たり前になりました。コロナウイルス以前には、デジタル化は、スタートアップ企業やIT企業などからゆっくりと浸透しているものでした。しかし、コロナウイルスをきっかけに急速な社会変革が行われています。本書で紹介する事例の中には、自治体がAI(人工知能)やロボットを導入した事例もあります。窓口業務があり、ペーパーレスがなかなか進まない自治体でAIが導入されることは社会変革の大きな証しといえます。
話は変わって、皆さんは、ドラマは見ますか。2009年と2011年 に『JIN - 仁 -』と『JIN - 仁 - 完結編』というドラマが放送されました。脳外科医の南方仁が、2000年の現代から幕末にタイムスリップして、幕末の医療を近代化させていくという、漫画を原作としたドラマです。その特別編が、緊急事態宣言の最中である2020年4月18日から5月13日に放送されました。土日の午後2時から3時間、3週にわたって計6回の放送枠だったにもかかわらず、すべての回で2桁を超える高視聴率をたたき出しました。脚本がよかったことはもちろんですが、作中で取り扱われた病が、コロリという伝染病だったことも一因と考えられます。その伝染病と戦う脳外科医の姿が、コロナウイルスに立ち向かう現在の私たちの心境に合致したこともあり、視聴率を伸ばしたのでしょう。
幕末当時、彼らには何の武器もありません。目の前にいる近代医療を知る南方仁先生だけが頼りです。けれども、現代は違います。今やインターネットが当たり前のように使われています。携帯電話は私用と会社貸与の2台持ち、PCも私用と会社貸与の2台、Apple Watchなどのウェアラブルデバイスを保有し、1人が全部で5台以上の情報通信機器を持っているのが当たり前のようになっている時代です。データ量が指数関数的に増大していき、SNSを開けば、世界でコロナウイルスがどのように拡大しているか、世界中の人々がコロナウイルスに対してどのように反応しているのかが手に取るようにわかります。データ量が増えると同時にPCの計算速度も圧倒的に速くなりました。データが増大し、拡散するスピードが速くなるのと並行して、PCが処理できるデータ量もけた違いに増えているのです。
その結果、私たちは新しい武器を手にすることができました。それが、本書のテーマであるAIです。バズワードのようにもなっているAIは、過去に何度も期待と失望が繰り返されています。AIが新しい武器になり得ることに対して懐疑的な人も多いかもしれません。しかし、今まさに社会変革が起きているのです。大企業でテレワークが浸透したように、社会にAIが急速に浸透しているのです。また、AIとともに、ロ ボットという武器も私たちは持っています。AIを搭載したロボットは、自律的に動きながらコロナウイルスと闘っています。ロボットには、医師、看護師の業務を一部代替する可能性も大いに秘めています。AIはどのようにしてコロナウイルスと闘っているのでしょうか。ロボットはどのようにコロナウイルスに立ち向かっているのでしょうか。現代の私たちが手に入れた武器は本当に強い武器なのでしょうか。
本書の構成
本書の第2章と第5章では、AIやロボットがコロナウイルスに立ち向かう多くの事例を紹介しています。多くの企業がそれぞれの技術を結集させ、コロナウイルスに対峙しています。異業種から参入し、コロナウイルスと闘う技術の開発をしている企業もあります。本書で紹介しているAIやロボットは、実際に実装されているもの、実証実験段階のもの、シミュレーションなどの研究段階のものを含んでいます。
第3章では、AIの論文をいくつか取り上げ、どのようなシーズが作られているの
かを紹介しています。論文の紹介は、簡単なものと、より詳細が知りたい人のために一部掘り下げたものと、2種類を用意しました。数式にまでは踏み込んでいないので、本書で物足りない方には出典を参照していただければと思います。事例紹介だけではなく、第7章では、現場のリアルな声を記載することで本書の内容に厚みを持たせました。台湾のIT担当大臣唐鳳(オードリー・タン)氏のインタビューは、本書の注目トピックのひとつといえるでしょう。世界の頭脳百人にも選ばれ奇才と称される同氏は、コロナウイルスに対抗するため、台湾で数々のデジタルツールを素早く実装させていきました。同氏の見るコロナウイルスvs.デジタルという視点は、今後のコロナウイルスとデジタルとの付き合い方を考えるうえで大いに参考になるでしょう。また、本書の著者の1人である石井大輔氏はコロナウイルス患者として医療現場で働く医師や看護師と接することになりました。現場のリアルな苦闘もエンジニアの視点からレポートします。第7章だけでも一読の価値 ありです。
また、vs.コロナウイルスのAIとロボットにとどまらず、第1章と第4章では、AIやロボットの 歴史、現在の市場についても紹介しています。そして、社会が変革する今この瞬間、AIやロボットがどういう方向に向かっているのか。第6章では、その将来展望も記載しました。
本書を読むことで、過去、現在、未来のAIとロボットの姿を概観することができます。これまでAIやロボットに触れる機会が少なかった人たちにもその進展を知っていただければと思います。そして、今後のAIとロボットの発展に思いを馳せてください。コロナウイルスという未曽有の緊急事態ではありますが、AIとロボットが作る未来の可能性に少しでも希望や勇気を感じていただければ幸いです。
本書は、素晴らしいメンバーに協力いただくことで短期間での執筆を実現することができました。日本最大級のAIコミュニティTeam AIを運営する起業家の石井大輔氏。今回、石井氏のネットワークがなければ本書は完成しなかっただろうと考えられます。同氏の素晴らしいチームビルディング力のおかげで短期間で本書を完成することができました。
そして、偶然にもドラマに登場した南方仁と同じ脳外科医であり、起業家でもある河野健一先生。AIを用いた医療用プログラムの開発を行っており、医師の視点とAIエンジニアとしての2
つの視点から本書の内容に厚みを加えてくださいました。そして、PhDを持ち、大企業の最前線でAI研究を行っている小西功記氏。AIに対する最先端の知識と深い理解によって、AI
の論文解説に厚みを生むことができました。最後に、多様なバックグラウンドを持つ4
人の共著という難しい取組みに伴走してくださった編集者の長谷川和俊氏に、この場を借りて感謝いたします。
2021年1月 著者を代表して 清水 祐一郎
共著者
異分野の専門家の共同プロジェクトです

清水 祐一郎
ITコンサルタント - NTTデータ経営研究所
所属:株式会社NTTデータ経営研究所情報未来イノベーション本部先端技術戦略ユニット(シニアコンサルタント)
1990年大阪府高槻市生まれ。
2015年東京大学総合文化広域科学専攻を修了。認知脳科学の研究に従事。2015~19年、PHC株式会社にて、R&Dと事業開発に従事。AIの研究開発とヘルスケアIT領域の事業開発を経験。
2019年10月より現職。現職では、民間企業と官公庁を相手に先端技術の戦略コンサルティングに従事。AIとロボットの社会実装、脳科学の社会実装、ヘルスケア
IT戦略策定など多くのプロジェクトに参画している。LinkedIn

小西 功記
AI研究者 - (株)ニコン
株式会社ニコン研究開発本部数理技術研究所 1982年和歌山県生まれ。2011年東京大学物理学専攻を修了。博士(理 学)。
大学在学中、米ローレンス・バークレー国立研究所にて観測的宇宙論の研究に従事。2011年、より高度な解析技術と精密光学技術から新たな未来を生み出せるのではとの思いから、株式会社ニコンに入社。
4年ほど半導体露光装置の開発に携わり、2015年より機械学習などを用いた画像処理技術の研究開発に従事。機械学習技術を用いた医学生物学の研究効率化を目指し、コンピュータビジョン技術を駆使した顕微画像処理技術を開発している。特許および国内外での学会発表多数。

河野 健一
医師・医療AI起業家 - (株)iMed Technologies CEO
株式会社iMed Technologies代表取締役
CEO医師(脳神経外科専門医、脳血管内治療指導医、脳卒中専門医)、MBA(グロービス経営大学院)。東京大学理学部数学科卒、京都大学医学部卒。脳神経外科医師として医療現場で16年間勤務。現場で脳血管内手術の課題を感じ、「世界に安全な手術を届ける 」と い う 理 念 を 掲 げ 、2019年に株式会社iMed Technologiesを設立し起業。くも膜下出血や脳梗塞に対する脳血管内治療のリアルタイム手術支援AIを開発中。

石井 大輔
AI起業家 - (株)キアラ CEO
京都大学総合人間学部では数学(線形代数)とフランス史をダブル専攻。伊藤忠商事ではミラノとロンドンに駐在。AI・機械学習に特化した研究会コミュニティTeam AIを立ち上げ。FinTech、医療などデータ分析ハッカソンやAI論文輪読会を毎週渋谷で開催。700回のイベント通じ会員8,000人を形成。
2019年、100ヶ国語同時翻訳ChatbotアプリKiaraを海外向けにローンチ。
© 2017 DAISUKE ISHII
MADE IN OKAYAMA 🍑 WITH LOVE ❤️